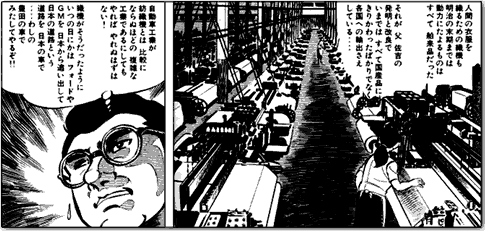| 第1話 |
-父佐吉と同じ挑戦の道を歩む事を決意-
当時の日本は市電、鉄道が交通機関の主流であった。しかし、大正12年9月1日、関東大震災でそれら全ての機能は停止。その中で、復興に重要な役割を果たしたのは自動車だった。「自動車はすごい。これからの交通機関を支配するものは、自動車に違いない」。廃墟の中で喜一郎はそうつぶやいた。
昭和4年9月、喜一郎は豊田自動織機製作所の常務取締役として、自動織機に関する特許の譲渡交渉を行うため、アメリカに渡った。ところが喜一郎は、本来の業務は、同行者に任せ、毎日、自動車工場、機械工場を見て回った。10年前には、欧州で誕生した自動車を強大な工業力をバックに自動車産業として確立させた時期のアメリカを見た。そしてこの時のアメリカの自動車産業は、成熟期に入り、高度な経営力を背景に世界に君臨していた。喜一郎は、佐吉から「わしは織機をつくってお国に尽くした。お前は自動車をやれ」といわれていたが、自動車よりも父の発明した自動織機を完成させることを優先してきた。その甲斐あって、輸入に頼っていた織機を逆に輸出する立場になり、その技術を欧米に供与しようというまでになった。自動車でうめつくされるアメリカを目の当たりにして喜一郎は、「自動車への夢」を実現するために全ての力を注ぎ込むことを決意した。